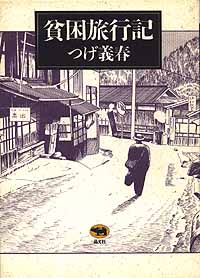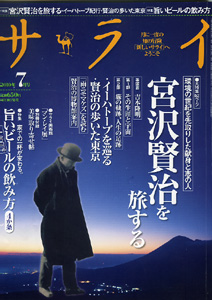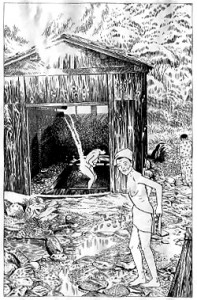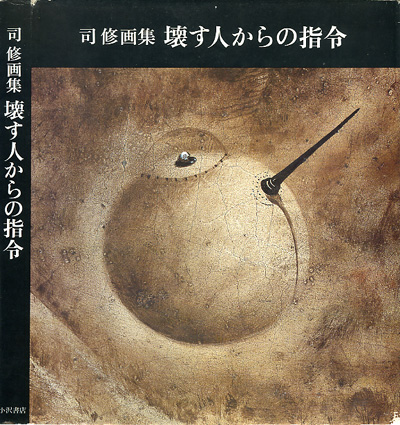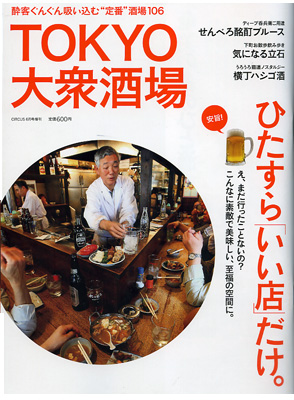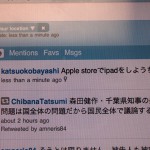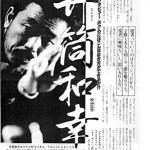「AKB48」と書いて「エーケービーフォーティエイト」と読ませる。2005年に誕生した秋葉原を本拠地として活動するアイドルグループの名称である。このプロデューサーがご存知、作詞家の秋元康氏だ。先日6月9日には「AKB48」の「総選挙」なるものが行なわれたと、スポーツ紙はじめワイドショーTVを賑わせている。ずっと2位に甘んじていた大島優子が昨年の1位前田敦子を逆転し優勝したという。選挙ブームにあやかってか「総選挙」などと名付けてイベント告知するやり口は、秋元康ならではである。
6月9日に開催された開票イベント会場では、2000名ものAKB48マニアが終結し、さながら政党の決起集会であったとされるほどの異様な盛り上がりなのである。投票結果の順位発表後の挨拶では、メンバーのほとんどが涙を流していた。これもまた秋元康によるプロデュースのたまものであった。
秋元康氏と云えば、かつて「おニャン子クラブ」をヒットさせたプロデューサーとして知られているが、当時の秋元は作詞家として関係していたTV番組「夕やけニャンニャン」の1スタッフであり、その大部を秋元に依っていたのは明らかであったが、しかしながらプロデューサーとして全てを仕切っていたのではなかった。当時のゴールデンコンビと呼ばれた一方の作曲家は後藤次利氏であり、おニャン子クラブの最人気アイドル、河合その子と結婚している。ちなみに秋元氏が結婚した相手もまた元おニャン子クラブの高井麻巳子であった。芸能作詞家として特段の才気を発揮していた秋元康ではあるが、芸能界で仕事を続けていく上での苦悩もにじませている。ブームが去ったあとの作詞家としては、やはり不安があったようでもあった。
そんなこんなの経過を経ての「AKB48」ブームである。つんくプロデュースによる「モーニング娘。」のブームを横目にしながら、新しい戦略として採用したのが「総選挙」戦略である。アイドル同士を競わせ、あるものには栄光を与え、あるものには屈辱の姿を晒していく。「総選挙」という名前を借りた芸能話題づくりの戦略なのである。
新しくナンバー1の称号を勝ち取った大島優子には見覚えがあった。藤原新也さんの初監督による映画「渋谷」に出演していたのだ。渋谷に巣くうギャルの一人として存在感のある演技が印象的であった。可愛いというよりもしたたかな「今」という時代のアイドル像を示しているようだった。