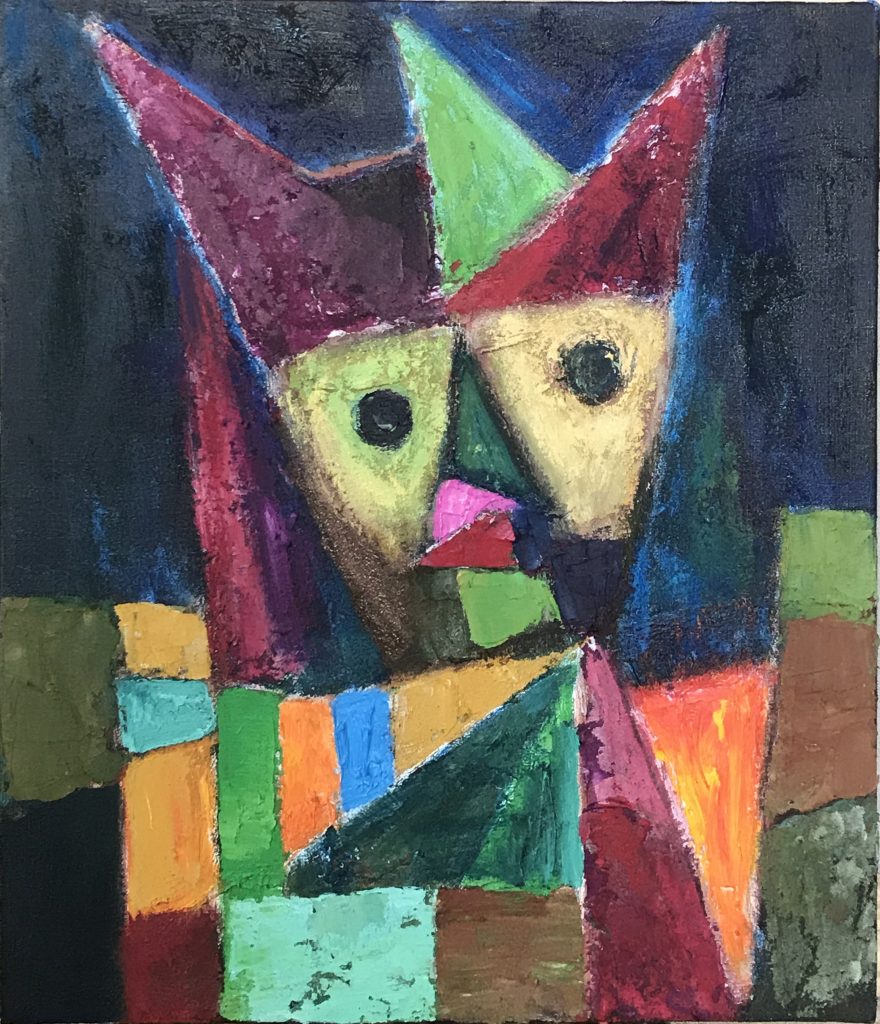常日頃から、里山に生息する蝶々たちには特別な関心を抱いている僕なのであります。蝶々たちが飛翔して舞う姿形は、この世にあってこの世のものとも思えないくらいに、特別なダンスの舞い也。ダンスするその姿は、決して人間には真似できないほどの高貴なものなのである。
そんな前後不覚の舞いを演じる蝶々たちに魅せられ、彼らの姿を連作している今日この頃です。特に白い羽根を羽ばたかせる白い蝶々は、人間の常識では解説不能の、神領域の舞いであると言ってよいのです。特異な、しかも優雅なる舞いは、追いかけるモチーフに相応しい。ずっとずっと描き続けていきたい。そんな気持ちにさせるのです。