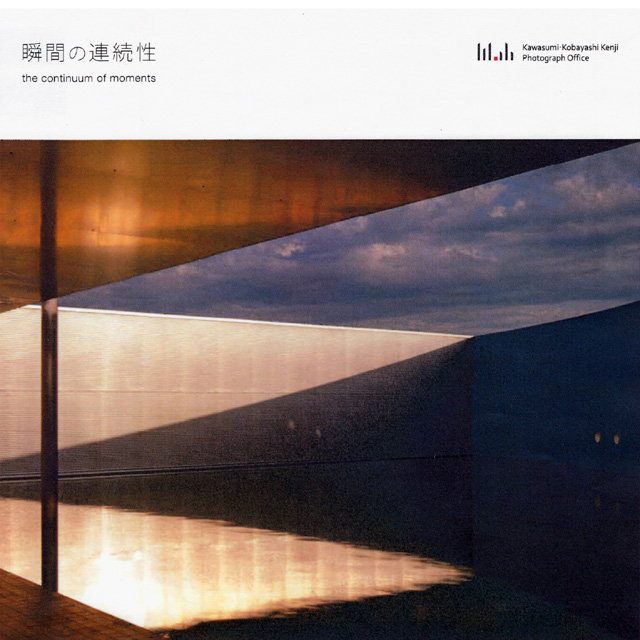[エラー: isbn:9784087205848:l というアイテムは見つかりませんでした]
中野剛志氏については昨年からよくTV番組にも出演していることなどから、顔と名前は知っていた。反TPPの論陣を張る若手論客という扱いで、その他のメディア、マスコミにもちょくちょく顔を見せている。
今回その中野剛志氏による「TPP亡国論」を読んだのだった。多少の期待感を抱きつつ読み進めたのでが、読後の心象は決して満足できるものではなかった。何やら上滑りした筆致がいたるところで散見され、それが妙に気になってしかたがなかったのだが、最後までそれを払拭することはできなかった。恐らくは彼の議論の相手は、狭小な経営学村の住民か、或いはスポットをやたら当て続けるマスゴミなどがターゲットなのだろう。だから狭小な村の住民やマスゴミの舞台に関心がないおいらには、ぴんと来るものが極めて少ないのだ。
TPP参加という選択が誤りであることを、括弧つきの「学問的」見地から様々に述べているのだが、何かそこには肝心のものが欠けている。例えば生きた人間の「血液」を想起させる記述が極めて少ない。学者、研究者に対する攻撃的、皮肉的な、孤児を演じる様的言動は、却って彼の人間的浅ましさを浮かび上がらせてしまっている。こういう人間が書くもの、発言するものに対しては、一定の距離を置くしかない。過大な期待などせずに、その言動の部分を利用すれば良いのである。げんに今のところ彼の論理は、正しいことを示しているのだから。
中野氏の論理は「あとがき」に集約されているので、その一部を引用してみたいのだが、本日はここまでにし、別稿にて記すことにする。