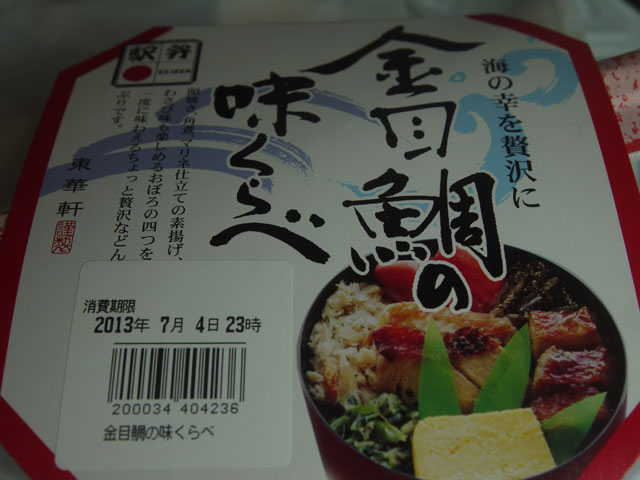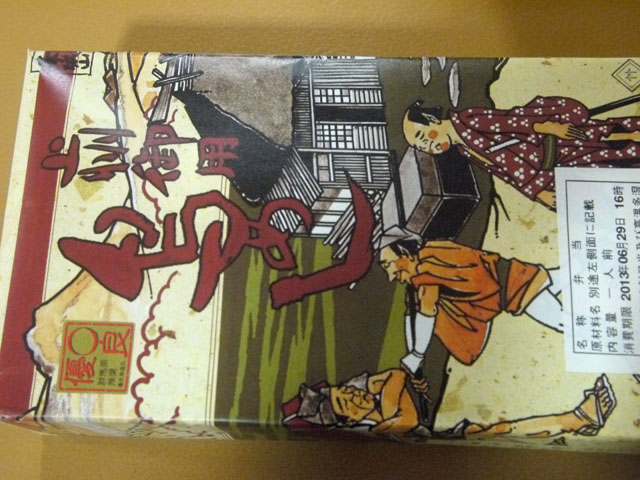[エラー: isbn:9784309021690:l というアイテムは見つかりませんでした]
またまた綿矢りささんの新作集「憤死」が発刊されたことを書店で知り、早速同書を読んでみたのだ。
4つの短編からなる作品集である。帯には「新たな魅力あふれる 著者初の連作短編集」とある。「著者初の」というのはその通りだろうが「連作短編集」というフレーズには合点がいかない。4つの作品はけっして連作的な要素で結びついている訳ではない。こんな曖昧な関係性を「連作集」としてひとくくりにすることはあり得べきなのであり、こんな適当な売り文句を冠して売り出してしまった同書籍編集者の常識を疑わせる。貴重な才能を葬りかねないくらいに酷い扱いであり、怒りさえ感じさせてしまうくらいだ。であるから、と強調する訳ではないが、以下には「連作集」ではない同書の魅力について、いささか述べていきたい。
物語の主人公は幼女だったり、少年だったり、妙齢の少女から大人にかけての女性だったり、少年の思いを引き摺って生きる男だったり、等々と多岐にわたっている。取り立てて企図されたテーマはないのだが、あえて述べるならば、人生のあるいは人間存在の裏舞台を、りささんなりの切り口で物語化させた作品集ではないかということだ。裏舞台は表舞台を眺めては色々と批評もしつつ、ときには恐ろしい結末に導いたりもする。順風満帆の人生にはおそらく裏舞台の存在は邪魔な存在であるのだろう。それでも存在を消されることなくある裏舞台の存在を物語として浮かび上がらせるりささんの筆致は見事である。
肩の力を抜いて、綿矢りささん的物語発想の展開そのままに綴られたと思われる短編集の数々には、少女感覚を過去のものとしてなお、其れらの感覚にこだわり続ける登場人物たちに遭遇する。
たとえば表題にもなった「憤死」という短編作品は、主人公の少女と、自殺未遂をした主人公の友人との関係性が主軸となって物語が進んでいくのだが、「好き」や「嫌い」を凌駕してその先にある女同士の遣り取りの機微に触れつつ、やはりりささん的な世界へと入り浸ってしまうのだ。