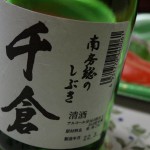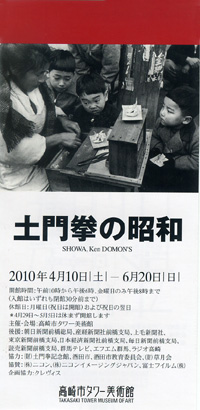八王子の「アートムーチョ」というイベントが雨で流れて時間を持て余していたとき、ふと岡本太郎の壁画に無性に会いたくなり、出かけたのです。渋谷駅と京王井の頭線の改札を結ぶ通路壁全体を覆うようにして設置されている。毎日30万人の人間の目に晒されるという、幅30メートル×縦5.5メートルの巨大な壁画だ。
もともとはメキシコの新しいホテルに設置される予定で制作されたが、財政難からホテル開業の見込みが無くなり、その後メキシコ国内の何処か判らぬ場所へと姿を消していた。それが母、岡本敏子さんの熱意が実って隠されていたこの作品が発見されたという。2005年には巨大壁画が分割されて日本へとわたり、修復作業も始まった。一般公開もされ、2008年秋には現在の渋谷での恒久展示が実現したのである。
糸井重里さんの「ほぼ日」サイトや他のニュースで壁画の存在は知っていたが、中々観に行く機会も無いままに徒なときを過ごしてしまっていた。やはり「腐っても岡本太郎」のことはある。と云うよりか想像以上の圧等的な衝撃を受けたと述べるべきだろう。この「明日の神話」は広島の原爆投下をイメージして描いたという説が強い。かつてフランスへ渡った岡本太郎はピカソの「ゲルニカ」に衝撃を受けたとされるが、ピカソを乗り越えるためのテーマが、この作品に凝縮されているのかも知れない。日本人である岡本太郎が「広島」に目を逸らすことはできないであろうし、そのことはまた彼個人としての芸術的野心にも裏打ちされていたと云えるだろう。岡本敏子さんも関連ホームページで、以下のようなメッセージを寄せている。
―――――
『明日の神話』は原爆の炸裂する瞬間を描いた、
岡本太郎の最大、最高の傑作である。
猛烈な破壊力を持つ凶悪なきのこ雲はむくむくと増殖し、
その下で骸骨が燃えあがっている。悲惨な残酷な瞬間。
逃げまどう無辜の生きものたち。
虫も魚も動物も、わらわらと画面の外に逃げ出そうと、
健気に力をふりしぼっている。
(以下略)
―――――
中央に聳える巨大な生き物はレリーフ状に浮き上がって描かれており、全く異界からの生物のようであるが、人間のように見えないことも無い。全ては「人間界」における事象、事案がテーマとなっているのだから、きっと人間そのものの変容したイメージを描いているのだろう。