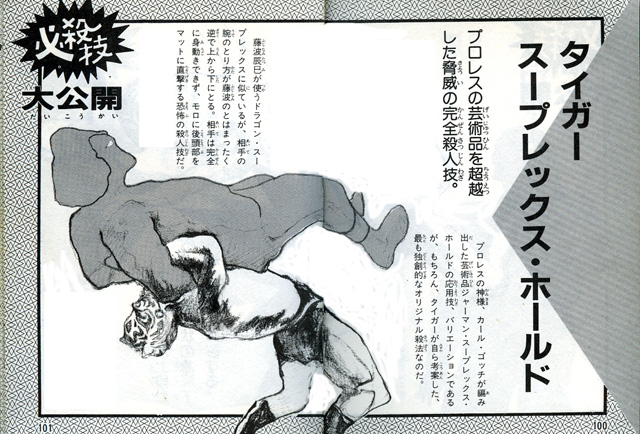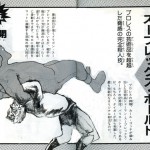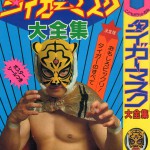大竹昭子さんの「図鑑少年」を読んだ。
[エラー: isbn:9784122053793 というアイテムは見つかりませんでした]
書店でふとして手にした文庫本を開くと、見覚えのあるモノクロの写真ページが目に飛び込んできた。かつて90年代にて栄華を誇った「SWITCH」というグラビア系雑誌に連載されていた写真であることが、解説文を読みつつ、次第に記憶の上に詳らかになっていった。1999年には小学館から単行本が出版されたとあるが、これには見覚えがなかった。おいらの記憶的ビジョンに鮮明に染み付いていたこの本の光景は、90年代のものとして焼き付いてしまっていたのである。10数年を経ての再会とでも云おうか、あるいは10数年間のワープを経てのドラマティックな再邂逅とでも呼ぼうか…。
各章を隔てる栞のように挿入されたモノクロ写真ページは、作家の大竹昭子さんが自ら撮影したものである。都会を散歩すればすぐにでも遭遇するような光景ばかりでありながら、けれども不思議な光景として目に焼きついてくる。都会風景の上面をじっと眺めてみたりすればするほど、裏面から湧き上がって我々の視線を釘つげにしてしまう不可思議な風景が染み付いて放さないのだ。
24編からなる掌編的物語のほとんどは、日常的な都会生活上にふと生じた違和感が語られていく。短い物語と物語とを繋ぐのはまた、時を隔てた時間であったりする。あるいは時と場所とをワープされた空間であったりするのだが、そのギャップに驚かされるとともに、不思議な物語的世界にはとても時めかされてしまったのでありました。