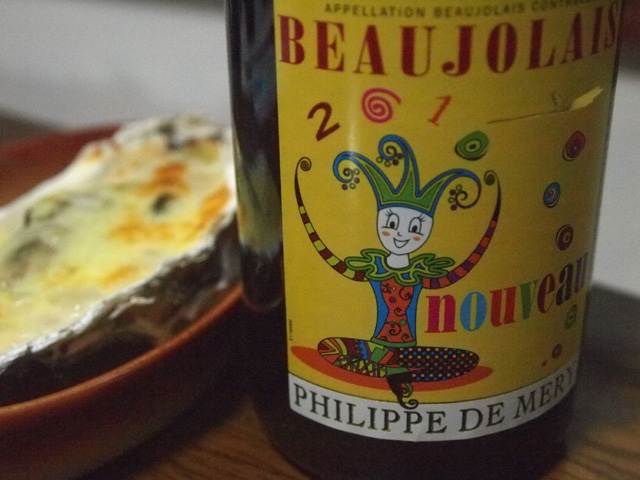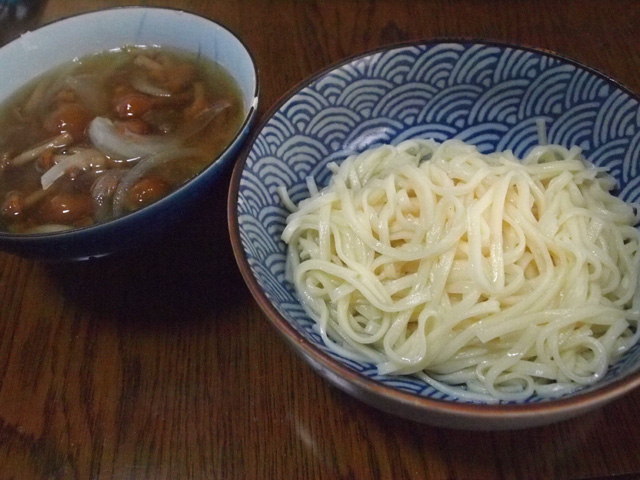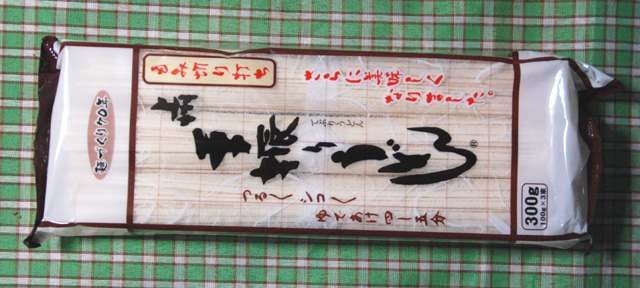この数日来の寒波襲来で、東京の街も着実に色づいてきた。近場の公園や裏山を散策するだけで紅葉の季節を実感する。東北を旅行して観た紅葉の美しさには敵わないが、それでも散策する行き先の処々で目にする、イチョウやモミジに見とれてしまうこともしばしばだ。
ビル街を通り越して公園を歩くと、どこからか「色づく街」のメロディが聴こえてきた。南沙織が1973年に歌ってヒットしていた曲だ。「17才」とともに彼女の代表的な曲として知られている。高橋真梨子、三田寛子、水野美紀、その他様々な歌手がこの曲をカバーして発表している。松田聖子がこの曲を歌ってアピールし、その後の歌唱賞を獲得したというエピソードは有名である。それにしても今なお、南沙織の楽曲が21世紀の今日に響いていようとは、発表当時の関係者の誰もが想像し得なかったことに違いないだろう。
作詞は有馬三恵子氏が手掛けている。芸能界での活躍は相当なものだが、作詞家のプロフィール、個人情報は、いまだ謎ばかりだ。名前だけの作詞家という存在があるならば、有馬三恵子氏はその筆頭とも目される。何ゆえにこれほど個人情報を秘匿するのかと、以前おいらは不思議だったが、今にして思えばこれぞ、賢い作家的戦略であったとも云えるかもしれない。
さて紅葉といえば、落葉樹が色づいた葉をその後に地面の上に落としていくのであり、そのイメージは「失恋」を連想させるのであり、必然的に失恋の楽曲へと繋がっていくのだ。南沙織が歌った「色づく街」は、まさにそのイメージを我が国の国民的感情として定着させるに値する、忘れられない名曲となった。日本人はとても失恋の歌が、詩が好きである。失恋大国日本の代表的な一曲となる可能性を秘めているのだ。