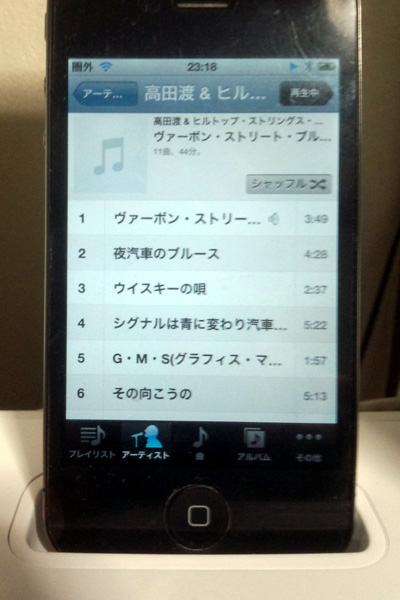[エラー: isbn:9784101388816:l というアイテムは見つかりませんでした]
今年の直木賞受賞作家こと辻村深月さんの「つなぐ」を読んだ。現在公開中の映画「ツナグ」の原作でもあり、社会的関心が高まっているだけにおいらも書店で買い求めてしまったという1冊ではある。
初めは単なる社会的ブームメントに対する一片の関心であったが、死者と生者、死と生、あるいは、死に向かう生、等がテーマであることを理解しつつ、一片以上の興味で読み進めることとなっていた。
登場人物は、主人公の「使者(「ツナグ」と読む)」こと渋谷歩美の他に、アイドル・水城サヲリ、サヲリとの再会を望むうつ病患者の平瀬愛美、演劇女子高生の嵐美砂と親友の御園奈津、癌で亡くなった母・ツルに会うことを希望する畠田、等々と多種多彩である。最終章では、主人公の歩美が死者への対面を望むというシチュエーションから章のスタートだ。物語は当初の短編集の装いを裏切って、連作長編小説の体を成して、読者の関心を引きずっていくのだった。
死者との再会を可能にすると云えば、青森の潮来が連想されるが、小説の初めから「潮来とはまるで違う」という記述がしつこいほど登場する。日本における土着的神話のイメージを峻拒していきたいという作家の志向を読み取ることが可能であろう。
何冊か読んでいる辻村深月さんの作品世界と同様に、同書もプロットがきっちりとしていて、それなりのレベルに達してエンターティメント性が顕著である。そんなエンターティメントを求める読者であるならば、充分に満足できる作品であろう。
然しながら、おいらは大衆小説のエンターティメントにはほとんど興味が無く、更には、死者との再会と云うシチュエーションは眉唾ものだと云う考えを持っている。或いは死者と生者をつなぐ使者(ツナグ)などは、フィクションの中でも出来の悪い代物だと考えているのだから、この力技が走る作品も、テーマとシチュエーションが空回りしている力技作品の一つであるという以上の評価を抱くことは無かった。